第5章 暮らしの移り変わり
第2節 低地で暮らす
■川と船 :綾瀬川
綾瀬川は昭和6(1931)年に花畑運河ができると、東京から埼玉県東南部の農村に行く船の主要な通り道となり、川砂や下肥を運ぶ船が数多く行き来していた。また一銭蒸汽もしくはポンポン蒸汽と呼ばれていた船が中川と綾瀬川を航行していて、小菅町や小谷野町に乗船場があった。この船は浅草へ行く人が利用していた注釈1。
綾瀬水門は綾瀬川と荒川を結んでいるが、上げ潮のときは綾瀬川から荒川へ入る船が通行しにくくなる。そこで小菅の水戸橋付近が船の潮待ち場になっていて、たくさんの船が下げ潮になるのを待っていた。かつては水戸橋の所にこうした船に乗る船頭に食料品などを売る船が停泊していた。
昭和20年代は綾瀬川の水もきれいで、水泳をする子どもも多く、京成線の鉄橋から飛び込みをして肝試しをすることがあった。
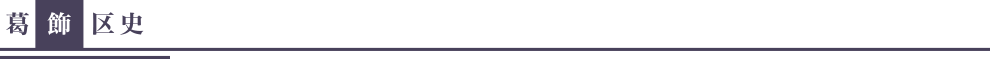
 音声読み上げ
音声読み上げ
