第5章 暮らしの移り変わり
第2節 低地で暮らす
■やっから :
ヨシなどが繁茂している湿地帯は「やっから」と呼ばれている。現在の西新小岩1丁目付近には大正時代まで広大なやっからがあった。ここに生えているヨシは萱屋根の材料として近隣の集落に売却されていた。地元の人たちはここを「六万坪」と呼んでいた。
現在の葛飾区総合スポーツセンター付近では、江戸時代に中川を付け替える工事があった。そのときに残された旧河道がやっからになり、奥戸新町の共有地になっていた。ここにはヨシが生い茂っており、冬になると集落の人たちが毎年1月に共同作業でヨシの刈り取りをした。ここは潮の干満が効くので、大潮の引き潮の時に手作りの下駄を履いて刈り取りの作業をした。刈り取ったヨシは共有地の地権者分の数の山にしておき、各家に分配して自宅の屋根材やヨシズの材料にした。昭和40年代にはここに東京の都心部から出たゴミが運ばれ、埋め立てられた。その当時は大量のハエが発生して周囲の家は騒然としたという。
水元猿町には中川の河川敷にやっからがあり、共有地になっていた。昭和30年代初期まで12月に集落共同でヨシの刈り取りをしていた。
水元飯塚町では河川敷のやっからで刈り取ったヨシを材料として和筆のさやを作る家が何軒かあった。ヨシの空洞になっている部分を利用して和筆の筆先にかぶせ、保護するものである。各家で製品をまとめ、都心の文房具店に出荷していた。
やっからの中にはヨシキリという鳥が多数生息していて、5月頃に繁殖期を迎えると鳴き声がうるさいほどであった。バンやクイナなどの水鳥の卵をとったり、出没する蛇に驚くこともあった。
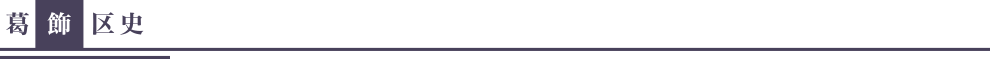
 音声読み上げ
音声読み上げ


