第2章 葛飾の成り立ち(古代~近世)
第3節 近世の葛飾
■葛飾の村 :村の景観
葛飾区域の村数は、17世紀半ばの正保国絵図に対応する『武蔵国田園簿』では30である。江戸時代の耕地は、「本田」と「新田」に分けられ、元禄検地以降に開発された新たな耕地は新田として把握された。「上之割」では小合新田、奥戸新田、曲金新田(後の細田)、鎌倉新田が早くから開発された。初め新田であった村々も、17世紀半ばの「天保郷帳」や明治時代初期の『旧高旧領取調帳』では、新田から村となった。また、分村もあり明治初期の『旧高旧領取調帳』では村数は約40となる。
近代の地図に当たるものが絵図であるが、領主の交代や村境の争いなどがなければ作成されず、大部分が幕府の直轄領であった葛飾区域の村が描かれた絵図は残っていない。ただし、享保 14(1729)年に、古利根川が付け替えられた上小合村には、河川や用水にかかわる絵図が残っている。絵図には必要な情報しか記載されず、方位や縮尺も近代以降の地形図のように正確ではないが、当時の地域の景観をうかがうことができる。
享保6(1721)年の「葛飾郡東葛西領上小合村絵図」では、萱野・道・川・藪・社が色分けで示され、丸囲みは「百姓」の屋敷地である。東に古利根川が流れる。河川敷に生い茂る萱野には幕府のための萱野があり、元禄10(1697)年の「亥刻上小合村萱勘定覚」には、「上之割」の普請にこの萱が使われていたことが記されている。
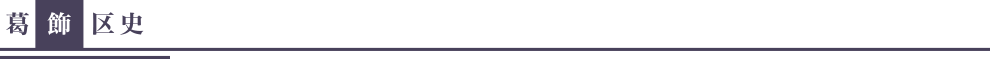
 音声読み上げ
音声読み上げ.jpg)
年上小合村萱勘定覚.jpg)