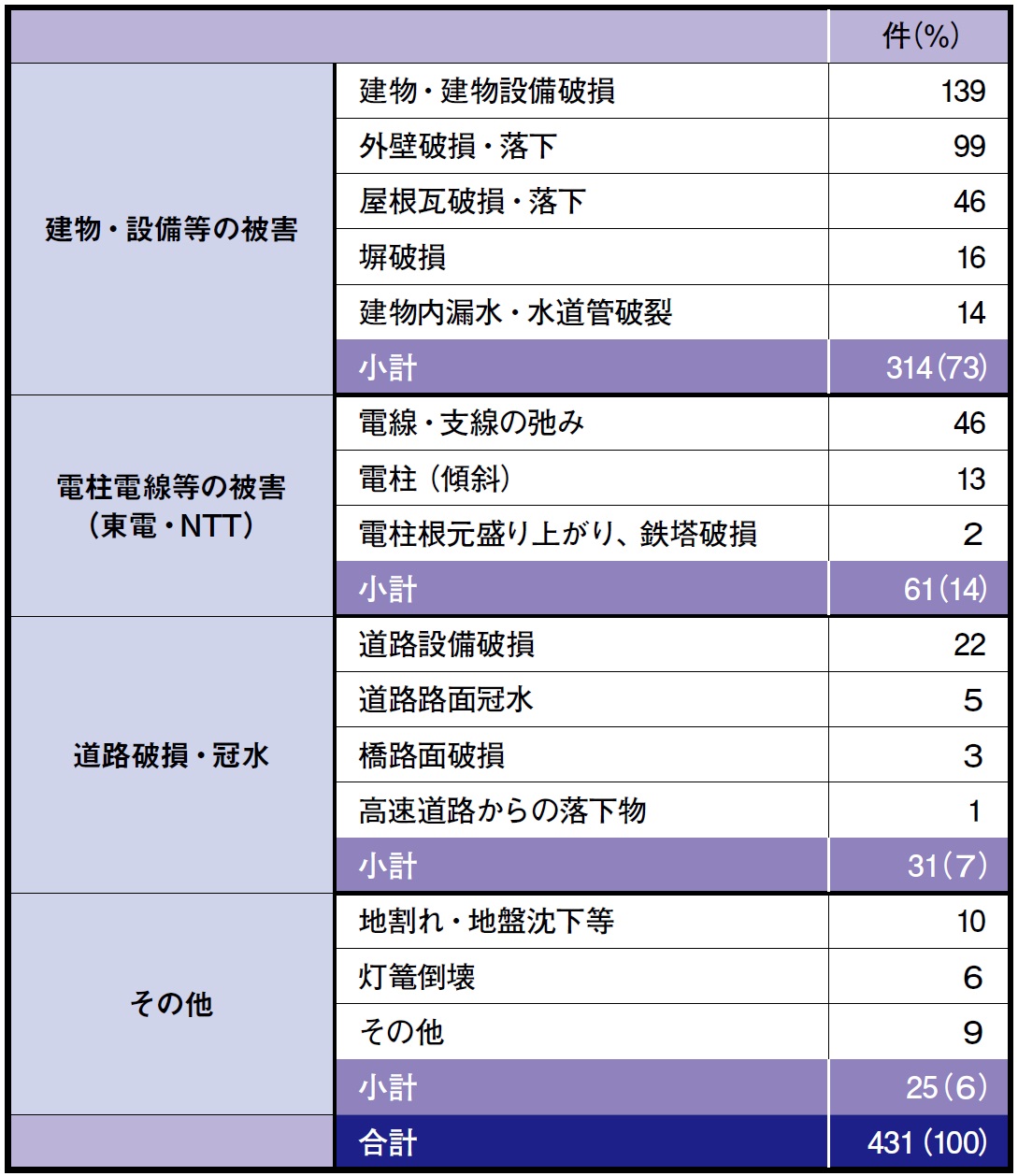第4章 現代へのあゆみ(戦後~平成)
第2節 現在の葛飾
■安全で安心して暮らせるまちづくりへ :都市型災害対策
平成7(1995)年1月17日に発生した阪神・淡路大震災は、6434人(平成18〔2006〕 年、消防庁確定)の命を奪い、住宅全半壊と全半焼を合わせて25万棟以上となる被害をもたらした。電気や通信、交通機関などのライフラインは壊滅的な打撃を受け、木造住宅密集地域では、建物の倒壊や火災が発生した。直接的被害のほか、避難所生活や子ども・高齢者や障害者への対応など震災の影響は多方面に現れた。
大都市で発生した大地震の被災状況を踏まえ、平成7(1995)年1月25日には、葛飾区は、「防災体制緊急見直し検討委員会」を設置し、防災対策の見直しに着手した。緊急措置として小中学校への備蓄品配備・防災無線設置、耐震診断の助成や家具の転倒防止器具の取り付け補助を開始注釈1-1した。平成8(1996)年には防災計画をより具体的かつ実践的なものに修正し、地域の防災体制の見直しを行った。
ハード面では、細街路拡幅事業や不燃化促進事業などに加え、平成10(1998)年度に東四つ木地区で密集住宅市街地整備促進事業を開始し、その後四つ木や東立石、堀切地域でも開始された。また、災害時のボランティアによる消火や炊き出し、応急活動の場として活用する防災活動拠点の整備や、火災の防止に向けた地下貯水槽の増設、災害時の情報連絡体制の強化策として、学校避難所への無線機設置やコミュニティ FM の設置などを進めた。
ソフト面においては、総合防災訓練を市街地対応型などの、より実戦的な訓練に変更するとともに、地域住民が避難所となる学校の運営方法を葛飾区の職員と話し合う「学校避難所運営会議」を設置し、訓練も開始した。各自治体と「災害時の相互応援協定」注釈1-2を締結し、救助体制を強化した。
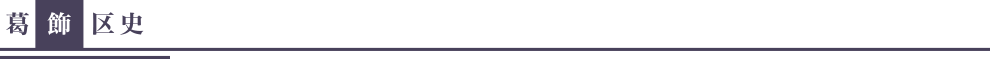
 音声読み上げ
音声読み上げ