第3章 地域の歴史
第8節 青戸
■ :青戸
青戸と青砥
地名は「青戸」ですが、駅の名前は「青砥」となっています。このちがいはどうしてできたのでしょうか。 「青砥」という文字は、青砥藤綱という鎌倉時代に活躍したといわれている名裁判官が江戸時代に人気者になって以降、多く見られます。この藤綱の館が青戸にあったとする言い伝えがあり、青砥という文字が多く使われるようになったようです。正式な地名はずっと「青戸」で青砥となったことはありません。
なお、青砥藤綱は実際にはいない人物で、後になってつくられたとされています。

浮世絵にえがかれた青砥藤綱(葛飾区郷土と天文の博物館所蔵)
戻る時は右上の×をクリックしてください

しめかざりづくり
葛飾の農家では、農作業が落ち着く11月ごろから、正月に飾るしめかざりづくりを行っていました。しめかざりは、地域によって種類や大きさがある程度決まっていました。
現在の青戸7・8丁目では明治時代にはほとんどの家でしめかざりをつくっていましたが、現在の青戸4〜6丁目では、大正時代になってからつくるようになりました。青戸でつくっていたのは、リンボウ(輪宝)という門松や井戸、お手洗いなどに飾られる小型の輪かざりでした。小型のものはつくるときに力がいらないため、なれた人なら一晩で500個以上つくることができましたが、値段が安いので、たくさんつくらないと収入が少ないものでした。青戸のリンボウは「青戸輪宝」とよばれて品質がよく、人気がありました。
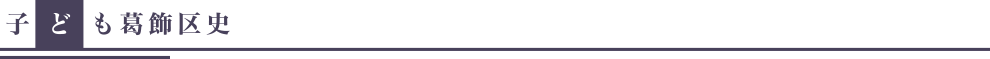
 音声読み上げ
音声読み上げ