第5章 暮らしの移り変わり
葛飾区の人生儀礼
誕生、結婚、死亡など人生の様々な節目に行われる行事を人生儀礼という。現在ではそれぞれセレモニー業者などが関与して行われているものが多いが、葛飾区内では昭和20年代ころまでは各家々を場として、江戸時代以来伝わってきた人生儀礼に関する行事を行ってきた。
1 葬送儀礼
(1)死亡から出棺まで
① 魂呼び
現在では人が亡くなったことは医師が判断する。呼吸の停止、脈拍の停止、瞳孔の拡大が死の判断基準であり、さらに平成9(1997)年からは、いわゆる脳死も死の基準の1つとされている。
かつてはこうした医学に基づいた死の基準とは別に、霊魂が肉体から離れることを「死」と考えたのではないかと思われるような行為が伝わっていた。
新宿では大正時代頃まで、人が息を引き取った直後に、家族が井戸に向かって亡くなった人の名前を大声で呼ぶことがあった。これを一般的には「魂呼び」と呼んでおり、蘇生を願う行為であった。
② 遺体などの処置
人が亡くなると、それまで闘病していた状態からたたずまいを改めて通夜を迎える。
まず遺体は、北枕にして安置する。胸の上にはかみそりなどの刃物を置き、手を合掌させる。生前、念仏をしていた人は合掌しやすいという。布団の上には亡くなった人が気に入っていた衣類を逆さに掛けておく。また霊場参りなどをしていた人は笈摺を掛けてやる。
遺体の胸元に刃物を置く意味は、刃物が魔物除けになるからである。その家の守り刀などがあれば一番良かった。遺体に取りつく魔物の多くは猫が正体であると考えられていた。そのため、葬儀の最中は猫を蔵の中などにしまいこみ、出さなかったという。猫が遺体に取りつくと、遺体が踊り出し、災いをもたらすと考えられていた。
③ 枕団子など
上平井では人が亡くなるとすぐに上新粉を材料として13個の団子を作り、亡くなった人がふだん使っていた飯茶碗に盛りつけ、頭の上に供えた。これを枕団子という。金町では枕団子の数は4個で、3つの団子を三角に供え、その上にもうひとつ乗せた。
また、枕飯と言って飯を山盛りに盛り付けたものに箸を立てて枕元に供えるという家もある。この枕飯は別火で調整すると言ってお客に出す料理とは別の鍋で作る。長寿で亡くなった人の家では、供える枕団子のほかにもたくさん作って近所の人たちや親戚に 配った。食べると長寿にあやかれるという。
④ 葬儀の手伝い
昭和20年代の水元では葬式を互助する五軒組合という家のまとまりがあって、葬儀の仕事を行っていた。この五軒組合だけでなく一般的にはズシ、ニワ、クミなどと呼ばれる近隣の家の人たちが葬儀の手伝いに出ることは区内の広い範囲で見られた。また、立石など都市化が早かった地域でも近隣の人たちが葬儀の互助をすることが基本であった。立石などでは隣組が主となって手伝いあいをした。
また、資産家の葬儀では、出入りの鳶職たちが葬儀を取り仕切るのが常だったが、食事の煮炊きなどは近所の人たちが行った。
葬儀の互助の内容は、まず葬儀の通知をすることである。これをツゲといい、2人1組で親戚などに通知をした。かつては電話がなかったこともあって、遠方の家には自転車で、近隣の家には歩いて葬儀の日取りなどを通知していた。通知を受けた家では、ツゲに来た人に食事をふるまったり、たばこ銭といって小遣いを封筒に入れて渡した。
このツゲの仕事は男の仕事であったが、「出世前の人にはツゲをさせない」といって若い人や奥さんが妊娠している人にはやらせなかった。
近隣の人のほかの役割としては、通夜、葬儀の時の参会者に食べてもらう食事の炊飯、出棺のときに行列に出る人が携えて持って行く作りものを作ることや墓穴を掘ること、棺を担ぐことなどがあった。
⑤ 六道
昭和初期まで水元、奥戸、南綾瀬などの農村部では土葬が行われていた。この土葬の準備は葬儀の仕事の中でももっとも重要なことであった。この役割を「六道」といった。
小合上町では六道は、五軒組合の人が順番で行った。この順番は帳面に付けておき、次の葬儀の時まで葬家が保管しておいた。
六道は墓穴を掘るときには腰に荒縄をまき、冷酒を飲みながら冷奴などをつまみにして作業をした。このときに飲む酒は残してはいけないと言って余ったら墓地に置いてきた。
棺は4人1組で担いだ。昭和初期まで座棺が主で、四角く、縦長の棺を大工やハヤオケヤと呼ばれた葬祭業者に作ってもらう。亡くなった人は胡坐をかいた形で納めた。座棺は埋葬するのに約6尺穴を掘らなければならないので「六尺」という言い方もある。埋葬が終わると六道には風呂に入ってもらって本膳のときには上席に据えてもてなした。「ツゲ」と同様に、20歳前の若い人や奥さんが妊娠している人は六道をやらせなかった。
また、資産家の葬儀は昭和の初めころから寝棺を用いていて、遺体を寝た状態で安置した。寝棺は担がずにリヤカーに載せて引いて墓地まで運んだ。
⑥ 葬祭業者
金町、亀有には昭和初期から葬祭業者があって、「ハヤオケヤ」「コシヤ」と呼ばれていた。コシヤとはコシ、すなわち棺桶を作る仕事のこと、またハヤオケとは亡くなった人が出てから素早く桶を作らなければならない仕事だからそのように呼ばれていた。昭和初期には大きな葬儀の時には出棺のときに放鳥といって鳩を放すセレモニーなども請け負っていた。
現在の四ツ木葬祭場(火葬場)が出来ると次第に火葬の家が増えた。金町あたりからも火葬場の煙突から煙が出ている様子がよく見えた。煙が立っていると「きょうも誰かがなくなった」と噂し合った。
⑦ 納棺
通夜が終わると納棺をする。まず家族などの近親者が湯灌をする。湯灌を行うときは部屋の畳を裏返しにする。体を清める湯は逆さ水といって水に湯を入れて温度を調整し、亡くなった人の体を拭き清める。湯灌に使った湯は縁の下など日の当たらないところに捨てた。
納棺するときには近親者が晒で作った襦袢を着せる。この襦袢は糸止めをしない。頭には三角の布をあて、六文銭、わらじ、頭陀袋などを入れてやる。六文銭は三途の川の渡し賃、頭陀袋はあの世に行くまでの弁当入れといった。また遺体の腕には「カンジオリ」といってこよりを付けてやる。これは数珠の代わりだといわれていた。
(2)埋葬
① 念仏
各集落には念仏をする仲間である念仏講があって葬儀の時は、通夜に枕念仏、出棺の時は門送り念仏、埋葬の時は穴端念仏などと呼ばれる各種の念仏を行った。
火葬に変わってからも、昭和40(1965)年くらいまではどこでも念仏講があって出棺して霊柩車に棺を納める間に念仏をした。


② 野辺送り
土葬の時代はお昼頃出棺した。棺は座敷から縁側に出し、出した後は座敷に塩を撒いて急いで箒で掃きだした。棺の上には笹に人形の色紙を下げたものをかざしていく。このほか紙で作った花や龍と呼ばれる竹で作った作り物を持って墓地へ行った。
葬列に加わる女性は白い着物を着て、男の近親者の人たちは編み笠を被り、白い紙で鼻緒を巻いた草履を履いていった。
埋葬するときは棺に荒縄を十文字にかけて静かに下におろし土をかけていく。区内の墓地は穴を掘り進めると水が出るところが多く、どこでも墓穴掘りには苦労をした。埋葬した上は土饅頭にしておき、目印に石を置き枕団子を供えておく。石を置く意味はキツネが墓穴を掘りかえさないようにするためだという。
一周忌にハカナオシといって石をどけ、石塔を立てる家が多かった。同じ年に2人亡くなった人が出た家では、埋葬するときに人形をいっしょに埋めた。
③ 忌中祓い
埋葬から帰ってくると忌中祓いもしくは本膳と言って食事を出した。葬儀の時はがんもどき、里芋、牛蒡などの煮ものに野菜のてんぷらが出された。この煮炊きをカシキバンといい、近所の人たちの重要な仕事の1つだった。
④ 流れ灌頂
身ごもった人が亡くなった時は流れ灌頂というものを作って供養した。水路の脇に4本の竹を立て、白い晒を張り付けてそこに亡くなった人の髪の毛を縛っておく。通りがかった人が経文を唱えながらひしゃくで水をかけてやった。
(3)法要
① 初七日
現在では埋葬した後にあわせて初七日の法要を済ませてしまうことが当たり前になったが昭和初期には葬式の七日のちに改めて初七日の法要を行った。このときは六道の人たちを上座に据えごちそうを出してふるまった。また念仏講の人が七日念仏をしてくれた。
② 四十九日
亡くなったあと四十九日は仏の魂は屋根の棟の上にいるという。四十九日に餅を搗く音を聞いてあの世に旅立つのだという。このことを「仏が支払いを終えた」といい、この日までに亡くなった人がこの世に残した未練を断ち切るものだといわれている。
この日は餅つきをし、49の餅を拵えて寺に届ける。上平井では49の餅とは別に大きな餅を一つ拵え、藁苞に入れて寺に納めた。また青戸では四十九日の餅を搗くと一つ大きな餅を作って藁につつみ両端を縛って寺に届けた。このときは誰かに見られてはいけないと言って、夜陰男の人が忍び込むようにして届けるものだった。
③ 半檀家
金町では特定の家で男女を別々の墓に埋葬する習わしがあり、これを半檀家と呼んでいる。男が亡くなると光増寺、女が亡くなると金蓮院に葬り、盆の棚経などはそれぞれ別々のお寺から僧侶がやってきた。また盆棚そのものも2つ作り、男の盆棚と女の盆棚と分けていた。僧侶には棚経の時間がかち合わないようあらかじめ打ち合わせをしておく。
④ 生まれ代わり
亡くなった人の股に名前を書いておくと新しく生まれてきた子どもの同じ場所にその名前の文字が現れることがあり、それを生まれ代わりといった。墓の土で洗うときれいになるという。
2 誕生と成長の儀礼
(1) 妊娠から出産まで
① 妊娠
妊娠したときは、姑に最初に知らせ、夫や舅、実家の親には姑から告げてもらうことが一般的だった。
昭和初期の農家では子どもが出来てもとくに気遣われることもなく、臨月まで働かされた。それでもいくつかの心構えや注意が姑から聞かされた。また、戦後は助産婦たちが妊婦の状態にあわせてこまかな注意をするようになった。食べ物に関しては、柿や梨は体を冷やすので食べない方がよいといわれた。
俗信的なことでは、葬儀に出るときは懐中に鏡を入れていくものだといわれた。葬儀の時に遺体に触ると生まれてくる子どもの同じ場所にあざが出来ると言われた。また葬列を見るものではないと言われた。懐中の鏡はこうしたさわりを防いでくれるといわれていた。
② 安産祈願
安産祈願に行く場所としてよく知られているのは市川市の手児奈霊神堂や日本橋人形町の水天宮である。こうしたお参りにも姑が一緒に行くことが一般的だった。真間の手児奈の手児奈霊神堂では安産祈願に来た妊婦に紐を授与してくれる。これを帯び祝いの時に腹帯とともに巻く。
また、日本橋の水天宮では腹帯を授与してくれるがそれが赤い布なら女の子が、白い布なら男の子が生まれると言われていた。無事にお産が済むとお礼を持って帯をお返しに行く。
③ 帯祝い
妊娠5カ月目の戌の日に帯祝いといって腹帯を締める祝いをした。このときは嫁の実家の人たちや仲人などもやってきてお祝いの飲食をした。また産婆がやってきて腹帯に「壽」の字を書き添えていった。
④ 産の場所
昭和20年代まで出産の場は家であることがふつうだった。
初めての子どもを産む時は、嫁は実家に戻り出産した。臨月まで働き、実家に帰るのは出産直前だった。
農家では、お産をする部屋は納戸と呼ばれる小さな部屋だった。納戸は座敷に隣接した小さな日が当たらない部屋だった。大正時代は電燈もなく、真っ暗な状態で、妊婦の状態が良く見えないような部屋だった。この納戸は、ふだんは若夫婦の寝室として使われていた。子どもが生まれるとなると、畳の上に油紙を敷き、サンボロと呼ばれた古い布で作った簡易な布団を敷いてそこに妊婦を寝かせて出産に備えた。
大正時代までは炬燵のやぐらや重ねた布団に妊婦が寄りかかって出産する座産と呼ばれる方法が普通だった。炬燵のやぐらなどを使う以前は藁束を21束作りそれに寄りかかって生むことが本来の方法で、産後はその藁を1日1つずつ外していき、すべて藁束が亡くなる21目がオビヤアケといって、産婦はこの日初めて産室から出ることが出来た。
⑤ 産婆
大正時代以前はトリアゲバアサンと呼ばれたお産の世話が上手な人に来てもらって出産の介添えをしてもらうことが一般的だった。昭和に入ってもお産の経費がたいへんだというので、職業産婆を頼まずにトリアゲバアサンで済ませてしまう人も少なくなかった。また、姑が取り上げるのが上手であればそれで済ませてしまった。昭和の初めころ、奥戸で職業産婆をしていた人の話によると当時は出産費用を払えない家は珍しくなく、お七夜に薄いお粥をごちそうしてくれて終わりだったこともあったという。
免許を持った職業産婆が出産の世話をするようになったのは大正時代の終わりごろで、高砂の市川産院などが始まりであった。職業産婆のことは「先生」とか「助産婦さん」と呼んでいた。昭和4(1929)年に刊行された『本田町誌』には25名の職業産婆の名前が記録されているが、そのなかでもっとも早く開業した人は大正8(1919)年である。
太平洋戦争が始まるころには概ねトリアゲバアサンに頼るお産はなくなり、昭和30(1955)年ころまで職業産婆が世話をして自宅で出産することが一般的になった。昭和25(1950)年刊行の『新修飾区史』によると当時の飾区助産婦会の会員は98名であった。また、当時19の産婦人科が区内で開業していた。
⑦ へその緒・後産
へその緒は油紙で包んで大切にとっておき、重大な病気にかかった時に煎じて飲むと治ると言われた。また嫁に行くときに持って行くものだともいった。後産は人に踏まれた方が良いと言って人が通るところに埋めた。太平洋戦争後は専門の業者がいて引き取ってくれた。また産湯は太陽の当たらないところに捨てると言い、産室の床下に捨てた。
(2) 誕生と成長
① 産婦の生活
21日は産をした部屋から出てはいけないと言われていた。産婦はなすやサバ、イワシなどあくが強く刺激のあるものは食べてはいけないと言い、味噌漬けやかんぴょうの煮たものなどをおかずにしておかゆを食べていた。
② 名づけ
子どもの名前は父親か舅が付けることが多かったが、浅草などに子どもの名前を売ってくれるおがみやさん(祈祷師)がいて、そこへ生まれた日時をいって名前を付けてもらうことがあった。
③ お産見舞い
産見舞いと言って産後すぐに近所の家や親戚から衣類、着物、布団などが贈られてくる。水元猿町には明治24(1891)年の産見舞い控え簿が残っていてこれによると産着、かんぴょう、かつお節などが贈答品として使われていた。
④ ミツメのぼたもち
出産後の贈答品として代表的なものがミツメのぼたもちと呼ばれるものである。これは産後3日目に嫁の実家から届けられるぼたもちで、重箱に一杯あんこがたっぷりとついたぼたもちが贈られてくる。産見舞いのお返しとしても使われた。嫁の実家ではこのために餅つきをし、近所の人たちにもふるまった。
ミツメのぼたもちを食べると乳の出が良くなると言い、産婦人も食べた。あまり甘いものを食べすぎると子どもの頭が甘くなると言ってきなこのぼたもちを混ぜる家もあった。
⑤ 母乳
母乳の出ない人はお粥や砂糖水などを子どもに与えていた。またもらい乳と言って近所の乳が余るような女性から貰うこともあった。
鯉を食べると乳が良く出るという言い伝えは一般的で、千住の川魚問屋から買ってきて料理をして食べる人もいた。また、乳が余った時はやたらなところに捨てず、南天の木の根元に捨てるものだと言われていた。
⑥ お七夜
生後7日目の祝いであるお七夜には赤飯や白いご飯を炊いてお祝いをした。この日までには名前を付けて神棚に貼りだしておく。この日は産婆を家に招き、お産の経費の精算をしたり尾頭付きの鯛を用意してお礼にしたりした。
⑦ 産着
生児の普段着として着せる産着には麻の葉の模様がついた着物を使った。麻の葉は魔除けになると言う。宮参りの時に着せる羽二重や色留袖の晴れ着を産着と呼ぶこともあるがこれは、嫁の実家から届けられた。
⑧ 床上げ・宮参り
産後21日を床上げ、あるいはオビヤアケといい、産婦人は産室から出ることが出来た。それまでは「ブクがかかっている」といって神棚の下は通れない、井戸水を汲むこともさわりがあるといって謹んでいた。ずっと風呂に入れないでいて、床上げの日は風呂に入って身をさっぱりとさせたという。
また、煉瓦工場、鍛冶屋など火を使う職業の人は奥さんが出産してから床上げをするまではさわりがあると言って仕事を休んだ。
また、21目には生まれた児の髪の毛を剃る。ボンノクボと呼ばれる頭頂部に近い1か所の毛は残しておく。これは囲炉裏に落ちた時、神様がそこの毛をつかんで助けてくれると言われていたからである。
宮参りは、21日目もしくは男の子は31日目、女の子は33日目に行った。その家の氏神である神社に行き、祈祷をしてもらった。大正時代には産婦人である嫁は宮参りに行っても鳥居をくぐらず、夫、姑、舅だけが子供を連れて参拝をした。
お宮に行く前に近所の家にあいさつに行くが、このときにおひねりを子どもの着物に縫い付けてくれる。これをイノハリコといって数が多いほど縁起が良いとされた。
⑨ 食い初め
生後100日目に食い初めをする。食い初め用の小さな膳椀に赤飯、鯛などを盛り付け、子どもにも食べさせる真似をする。この日の祝いは家族だけで行い多くの人たちを呼ぶことは少なかった。
⑩ 初誕生
生まれて1年目に一升餅をつき、子どもに背負わせる。このときは転ばないとよくないといって、子どもが転ばないときは襟をひっぱってわざと転ばせる。この日は餅つきをするので近所の人に「きょうは誕生餅だから」といって振る舞いをした。
⑪ 初節句
初節句には嫁の実家から雛人形、破魔弓(女の子)、内幟、5月人形(男の子)が贈られてくる。また、初正月に羽子板を贈ってくる家も多い。お返しには菱餅(女の子)、
柏餅(女の子)に干し鱈を付けた。
⑫ 捨て子
親が42歳の時に2歳になる子どもは「42の2つ児(しじゅうにのふたつご)」という。「42のはじかきっ児」などともいって、よくないこととして1度子どもを捨てることがあった。この時は屑掃きに使う箕の中に入れ、家の近くの辻(道がふたまたになったところ)に捨てる。あらかじめ打ち合わせておいた人に拾って貰う。この時に拾って貰った人とは拾い親としてつきあいを持った。
⑬ 夜泣き・疳の虫
新宿の日枝神社の境内には「夜泣き稲荷」という稲荷神社があって子どもの夜泣きがやまないときはお参りに行った。また金町では三峰講の講元が疳の虫封じをしていた。
また、藁を叩く横槌に紐をつけて家の周りを引き歩き「よっちゃん夜泣け~ちゃん昼泣け」というと夜泣きが治るといわれていた。
3 婚姻習俗
(1) 出会いから結納まで
① 仲人
昭和20年代まで、見合い婚が一般的で、まず相手を紹介してもらうことが多かった。紹介してくれるのは、行商人や保険の外交員、馬の仲介をする博労など広く世間を渡っている人たちだった。
「~に何歳くらいの娘さんがいるからどうだ」という話を聞くと、それとなく会いに行き、きっかけがあれば話し込んできて気に入らなければそれでおしまい。その気があれば紹介してくれた人に話して、話を進めてもらった。
こうして紹介してくれる人をハシカケと呼んでいた。結婚することになったときはこのハシカケがそのまま仲人をすることが多いが、別に仲人を頼むこともあった。いずれにしても婿方・嫁方双方に仲人を立てるので結納のころには仲人を整える。
ハシカケには仲人を務めてもらってもそうでなくてもお礼をするので何組もハシカケをしてくれる人のことは「あの人は仲人商売だから」と揶揄する人もいた。
葛飾区は水田の耕作に使う馬を北総台地の村から借りて使う人が多い。その馬を仲介する博労という仕事をする人がよくこのハシカケをした。
昭和14(1939)年に現在の三郷市早稲田から下千葉に嫁入りした人は、近所に住む博労に話を持ちかけられた。この人はあだ名を「ホラショウ」と呼ばれている人だった。博労という商売はあまり良い馬でなくても「この馬は働くぞ」といって押し付けてしまうことが常で「あの人はホラばかり吹いている」というので「ホラショウ」というあだ名をもらったらしい。「ホラショウのいうことだからあてになんねえ」というので、親戚の人にわざわざ下千葉まで様子を見に行ってもらった。「あまり大きな家でもないけどまあまあの家だった」というので話を進めてもらったが、あとで話を聞いた博労のホラショウさんは「俺のことをホラ吹きだっていうが俺の名前は8里先の村の奴らだって知ってるんだ」と憤慨したという。
こうしたハシカケの紹介を、ふつうは何回か経験してだんだん自分の分際というものがわかってきて、あまり高望みもせず、落ち着くところに落ち着いて嫁婿取りの相手は決まるものだという。
大正時代は盆踊りが男女の出会いの場だったという。奥戸では盆踊りのことをボンホーイというが「今日は娘っこの尻を狙ってやる」といって若者たちが張り切って出かけて行った。しかしこうしたことが結婚にまで発展することはまれだったという。
仲人には結婚後何年か盆暮にあいさつにいくが、それほど濃厚なつきあいはしなかった。
② 見合い
話が半ばまとまるとこぎれいな料理屋などで見合いをすることになる。男女とも親はいかずハシカケ、仲人などが引き合わせる。大正時代以前は嫁方の家で見合いをするということが多かった。
このときは娘がお茶を出し、若者がそれを飲むと結婚承諾ということになった。それ以前に親たちがネギキといって家のことなどを調べて置き、見合いの日には事実上決まっていることが多かった。
③ 自由恋愛
太平洋戦争以前は男女の恋愛が結婚に結び付くということはあまりなく、「あいつらはクッツキアイだ」とか「自由恋愛だ」などといって当たり前ではないような目で見られたものだった。
よその土地に出た娘がそこで見初められ、自由恋愛を経て結婚することを「おひきずり」といった。「あいつはひきずって帰ってきた」などといってこれもあまりよくは言われなかった。
④ アシイレ
結婚が決まった後、結納前に嫁が婿方の家に入り同居を始めてしまうことをアシイレといった。仮祝言をあげる家もあったが、なにもしないで嫁が婿方に移ってしまうことが多かった。また、泊らずに嫁が婿方に通い、仕事を手伝って夜は自分の家に帰るという例もあった。いずれにしてもアシイレのあとに話が壊れることはまずなかった。
世間の人たちもアシイレが済んでいると夫婦と認めていた。
⑤ 結納
農家の婚礼は年の暮れから翌年の田うないまでに行う家が多かった。そのため結納は稲刈りが終わると日のいいときを選んだ。
嫁方からは結納品と帯代が婿方に贈られる。結納品は、昆布、末広、するめ、とも白髪(麻)、偕老同穴(海老)などで、松戸や千住に行って買ってきた。また酒の入った角樽をふたつ酒屋で誂えてくる。
仲人、両親、場合によると親戚まで出席するのでこの日が両家の顔合わせということになった。
(2) 祝言
結婚式のことは嫁取り、婿取り、祝言などというが、ここでは一般的な嫁入婚のことを記す。
① 嫁の荷物
嫁の荷物は祝言の10日ほどまえの良い日を選んで、婿方の近所の人たちが受け取りに行く。この人たちを荷宰領と呼んでいた。嫁の荷物はタンス、長持ち、はさみ箱などに着物、ふとん、蚊帳、たらい、張り板などをまとめる。荷物は七、五、三の数にまとめリヤカーやオート三輪に積んでいく。数が多い方が財産が大きいことを示すので嫁の親たちはこの日のためにふとんを誂えてやったり、努力して荷を増やしてやった。
荷宰領たちは荷物の受取証を預かり、この日は嫁方でごちそうになって帰ってくる。オート三輪の運転手が泥酔してしまい、運転を誤って川に落ちてしまったという話がある。また、泥酔して寝込んでしまい、結局帰って来れなかったという話もしばしば聞く。荷物を受領しに行くことが大きな祝いであったことがわかる。受け取った荷物は、婿方の家の座敷に陳列して披露する。
_sトリミング.jpg)
_sトリミング.jpg)
② 婿入り
嫁取りの午前中、婿と親戚、婿方の仲人が嫁の家に嫁方に迎えに行く。これを婿入り、あるいは迎え新客などと呼んだ。嫁方の家で、双方の顔ぶれを紹介する。婿方の人数は7人と5五人とかの奇数の人数に整え、かつお節などを土産に持って行く。
嫁方の家ではちゃんとした料理を出し、酒もふるまって婿方をもてなすが婿は早々に帰ってしまう。そのほかの人たちも嫁入りの前までには帰り、嫁入りの行列は嫁方の親戚、両親、仲人たちだけである。
③ 嫁入り
嫁は文金高島田に角隠し、留袖の着物を着ていくことが多かった。履物は白足袋に草履である。
太平洋戦争が始まるころには婿は国民服を着て結婚式に臨むことが多くなったが、嫁は着物だった。昭和40年代にはウェディングドレスも見られるようになり、水元などではまだ家で結婚式を挙げる人たちが多かったが服装には洋装も見られるようになった。
また、昭和10年頃からタクシーを使って嫁入りする人が多くなった。
嫁は婿方の家に着くと台所に設けられた入口から家に入る。ほかの一行は縁側から座敷に入るが嫁はすでにお客の扱いではないということである。家に入るときは菅笠を嫁の頭に挿しかけ、地面にはたいまつを焚いてそれをまたいで家に入った。
嫁は家に入るとまず仏壇にお参りし、線香をあげた。
(写真3:嫁入りの衣装を着て歩く。昭和20年代、堀切で撮影。)


_sトリミング.jpg)
_sトリミング.jpg)


④ 祝言
祝言は家の座敷に屏風を立てて、一番上座の右に婿、左に嫁が座り横にはそれぞれの仲人が座った。そこから双方の本家の主人、分家の主人、親戚たちと並びそれぞれの両親は一番下座に着座する。
まず、オチツキノボタモチと呼ばれるぼたもちが出されそれを食べた後三々九度の盃となる。盃に酒を注ぐのは近所や親戚の小さな子どもたちで、嫁には男の子が、婿には女の子が水引のついた湯桶で酒を注ぐ。盃に酒を注ぐ子どものことをオチョウ、メチョウという。
まず、夫婦盃、次いで親子盃。兄弟盃をかわす。これらの盃ごとは障子を閉め切って行い外からは見えないようにするが、集落の若い衆たちが外からのぞくのが常だった。
⑤ 祝言の料理
祝言の料理は近隣の人たちが出て準備をした。また、魚屋に頼んで料理を作ってもらうこともあった。家の外で煮炊きをし、組み立て式の棚に出来上がったものおいて座敷に運ぶ。戦後は魚屋に仕出し料理をあらかじめ作ってもらう家も多く、かまぼこ、ようかん、鯛、きんとんなどが主流だった。こうしたときも近所の人たちが煮しめを作りその助けとした。また、お土産用の二の膳を用意し、かつお節などを付けた。宴は夜半まで行われるのが常で、夜明けまで飲んでいる人がいることは珍しくなかった。
昭和30年代から柴又の料理屋などを祝言の場とする家が多くなり昭和40年代には区民会館での祝言が人気を呼んだ。
⑥ 祝言での出し物
これさま、高砂、そうだよ節などの歌が披露された。また、万作踊りが出しものとして踊られた。
⑦ ヨメビロメ
祝言の翌日、手伝いに出てくれた近所の人たちを招いてヨメビロメが行われた。この日の朝嫁は舅、姑に付き添われて神社にお参りに行き、帰ってくると座敷に集まった近所の人たちに手ずから茶を入れる。ヨメビロメで嫁を紹介する役割をテシキといって親戚の女性が勤めた。
ヨメビロメは女の仲間入りと言ってこの日の座敷にはおもに奥さんたちが集まった。また、祝言に呼ばれた親戚が嫁婿を招いてごちそうすることがあった。これをハデッカエシといって嫁は頭を島田に結い、嫁入りの格好をして出かけた。
⑧ ミツメ
結婚式後3日目をミツメといって嫁が里帰りをした。この日は姑が手土産を持って同行し、泊らずに帰った。
また、5日目、15日目などに髪洗いと呼ばれる里帰りをすることもあった。髪洗いは嫁が1人で帰り、1日か2日泊ってきた。
髪洗いが終わると、嫁としての暮らしが本格的になり、家での労働が本格的になる。
農家では田植えの季節になると嫁は手伝いに来てくれた人たちに弁当を作ったりして忙しくなる。また、新しい嫁はやの字に帯を締めるのが決まりで、初々しく働くので「ああ、このうちは新しい嫁さんが来たんだ」とすぐわかる。その可愛らしい嫁さんが、それから1年たつとすっかりやつれ、げっそりとしてしまうのが常だったという。
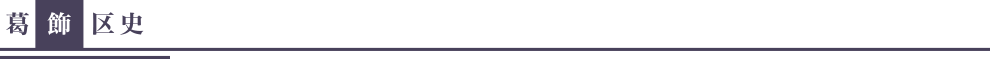
 音声読み上げ
音声読み上げ